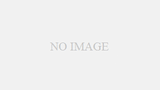個別キャッシュフロー
12問中4問しか正解しておらず、A問題を3問落としている。A問題の復習を優先して。
税引前当期純利益
PLの当期純利益に、PLの法人税等を加え、PLの法人税調整額を調整する。法人税等調整額が貸方になるとすれば、以下のような仕訳が切られているので、その分を差し引くことになる。
| 繰延税金資産 9200 | 法人税等調整額 9200 |
法人税等の支払額
| 支払 125,000 | 前期末未払額 60,200 |
| 当期末未払額 1,000 | 当期PL 8,900 |
有形固定資産の売却による収入
仕訳を有形固定資産勘定に反映できていない。
| 減価償却費 46,700 | 有形固定資産 46,700 |
| 減損損失 25,800 | 有形固定資産 25,800 |
有形固定資産勘定
| 前期末簿価 225,800 | 売却 15,300 |
| 減価償却費 46,700 | |
| 取得 291,800 | 減損損失 25,800 |
| 当期末簿価 429,800 |
投資有価証券
その他有価証券評価差額金は、前期末を当期に洗い替えするので、前期末の洗い替えの仕訳、当期末の分の仕訳を考える。
| 前期末分(その他有価証券評価差額金) 15,000 | 投資有価証券15,000 |
| 投資有価証券 ✕✕✕ | その他有価証券評価差額金 ✕✕✕ |
投資有価証券勘定
| 前期末 ✕✕✕ | その他有価証券評価差額金前期末 ✕✕✕ |
| 取得 ✕✕✕ | 売却 ✕✕✕ |
| その他有価証券評価差額金当期分 ✕✕✕ | 当期末 ✕✕✕ |
配当金の支払
別途積立金がある場合、下のような繰越利益剰余金の勘定になる。
| 繰越利益剰余金 ✕✕✕ | 別途積立金 ✕✕✕ |
| 配当 ✕✕✕ | 前期末BS ✕✕✕ |
| 別途積立金 ✕✕✕ | 当期純利益 ✕✕✕ |
| 当期末BS ✕✕✕ |
減損損失
減損損失を求める際に、割引前キャッシュフローと期末簿価を比較してしまった。⇒間違えないような下書きの作成を行う。
| 減損の兆候 | 割引前CF | 回収可能価額 | 減損損失 | |
| A | ○ | ✕✕✕ | ✕✕✕ | ✕✕✕ |
期末簿価を求めるためのタイムラインをしっかり書く。
将来キャッシュフローを求めるためのタイムラインをしっかり書く。
連結会計
23問中5問しか正答していない。A問題の取りこぼしが7個もあるので,復習必要
持分の売却
売却後も連結関係が残る⇒資本取引として資本剰余金勘定を用いる
| ↗ | 売却益 | 1023(取消) | ↘ | |
| 個別 | ⇒ | 連結持分 | ⇒ | 売却額 |
| 1980 | 2550 | ⇔ | 3000 | |
| 資本剰余金450 |
法人税等の調整が必要になる,法人税等を直接調整する。
| 資本剰余金 135 | 法人税等 135 |
持分法の一部売却
売却後連結関係が解消⇒評価差額とのれんを取り崩す,損益取引として扱う
| 個別 | ⇒ | 持分評価額630 | ⇒ | 売却額 |
| 550 | 634+(評価差額の取崩分△14)+(のれんの取崩分10) | ⇔ | 700 | |
| 売却益70 |
持分の売却
連結状態から連結関係が解消⇒評価差額は全部時価評価法で考慮されているので,のれんのみ取り崩す,損益取引として扱う
| 個別 | ⇒ | 持分評価額 | ⇒ | 売却額 |
| 5,500 | 7,250 | ⇔ | 8,000 | |
| 売却益750 |
期末のれん1,200×5/8(持分全体のうちの売却割合をかける)=750を足した金額7,250が持分評価額の売却相当額。
一方,残った持分(例えば,80%のうち50%を売却し,30%残ったケース)は,期末の純資産(新株予約権を除く)13,000に30%をかけて,のれんの残存部分(1,200×3/8=450)を加えた金額になる。
注意点:のれんの売却分,残存分の求め方は,のれんに持分80%のうち50%分として計算する必要があり,売却割合をそのまま掛けてはいけない。